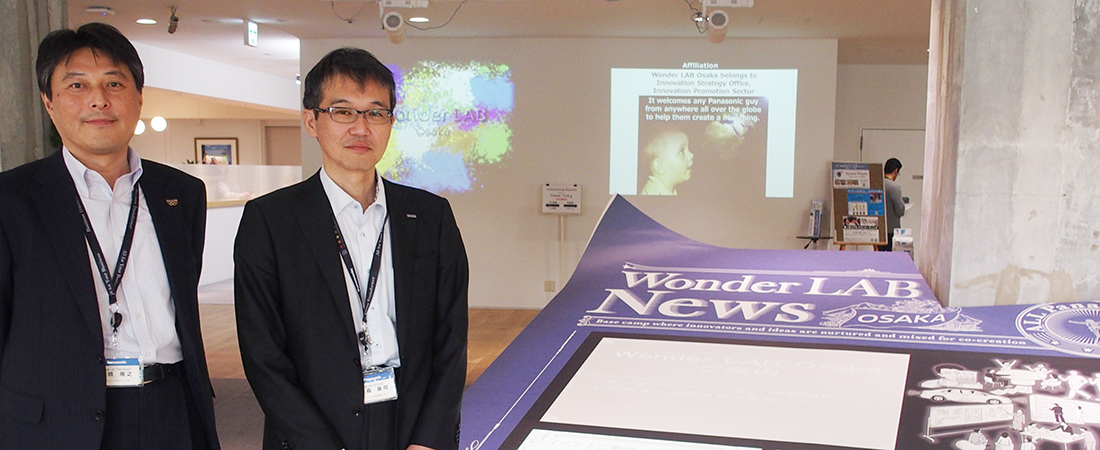
-
パナソニックIPマネジメント株式会社
人材開発部- 部長
- 高橋 隆之 氏
-
パナソニックグループ
イノベーション知的財産センター 知的財産部 戦略課- 課長
- 大森 基司 氏

転職情報
サービス概要
その他
閉じる
パナソニックグループ
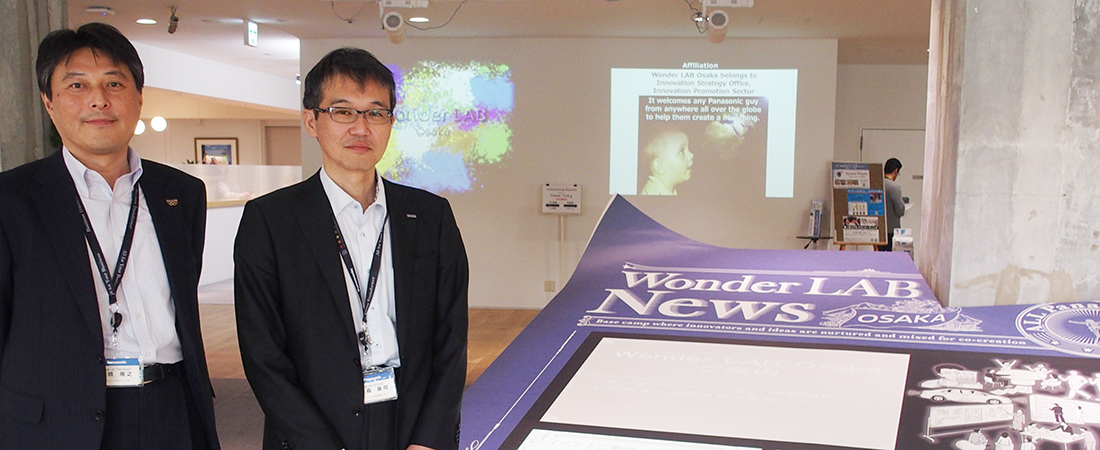
パナソニックIPマネジメント株式会社
人材開発部
パナソニックグループ
イノベーション知的財産センター 知的財産部 戦略課
1918年、創業者・松下幸之助氏が、家庭での電気供給口が電灯用ソケット1つだけだった時代に、画期的な2灯用差し込みプラグを発売してから101年。より良いくらし、より良い世界の実現に向け、電化製品を中心に次々と開発し世に送り出してきたパナソニック。その創業者の理念は守りつつ、家電メーカーから次のステージに変革を図っている。中でもパナソニックの知的財産部門は、特許庁への特許出願件数上位に位置しており、発明という事業の大きな鍵を担う重要な部門。パナソニックの知財実務を一手に引き受けているパナソニックIPマネジメントの高橋氏と、知財戦略を担う大森氏に、現状とこれからの展望をお伺いした。

高橋氏:昨年100周年を迎えて、会社のあるべき位置、目指す姿を津賀社長が今の言葉で表したのが「くらしアップデート企業」という言葉です。お客様の「最適」を追求し提供し続ける企業であるパナソニックは、創業当時から電化製品でお客様のくらしの「最適」を実現してきました。
今は、お客様の価値観が変わって来ています。お客様の変わっていくニーズに合わせて変化する「アップデート」企業になっていきたいと考えています。
振り返ると、パナソニックの草創期から30年ぐらいは「アップデート」企業だったと思います。主婦を家事労働から解放するために、要望の多い電化製品で色々な商品を素早く開発して、世に出す。そのビジネスモデルで成長してきました。その後、我々がそのビジネスモデルに甘んじていたところもあり、新しい価値を提供する「アップデート」ではなく、製品の性能を高める「アップグレード」になりがちだったかもしれません。101年目を迎え、草創期を忘れず、お客様の「最適」を目指してスピーディに「アップデート」する企業として気持ちを新たに生まれ変わるところです。
高橋氏:新事業区分では、基幹事業、再挑戦事業、共創事業の区分を設けました。3つの基幹事業でソリューション型事業を拡大していきます。
1つめはHomeX(ホームX)を1例とした空間ソリューション。家をまるごと、家電も含めて、ひとつの空間でお客様にとっての最適を提供いていきます。
2つめは現場プロセスソリューション。これまで製造現場のソリューションを提供してきましたが、それを広げてBtoBの様々なシーンで顧客の最適を提供します。
3つめはそれらを支える部品、インダストリアルソリューション。
この3つを今後の基幹事業として主力に据えました。また、再挑戦事業はこれまで3年間で投資をしてきたオートモーティブ、車載電池など、投資をしたものを回収できるよう収益性改善を目指します。また従来のBtoCの家電と住宅は共創事業と位置づけ、当社だけでなくパートナー企業や地域と連携してトータルで提供していきます。

大森氏:強みとしては会社として扱っている商品や事業の幅が広い。社内に様々なジャンルの専門家がいます。特にHomeXは過去の蓄積を生かしており、広くお客様のくらし空間に入り込んでいる当社製品がユーザーとのタッチポイントを持っているという点を大きな強みとしています。そこから解ることがユーザーへの最適化への第1歩となります。
高橋氏:IOTの時代、データが大きな価値を持つが、我々は今までのお客様とのお付き合いの中でたくさんのデータを蓄積しています。それを将来のお客様にとって最適なものに繋げていこうとしています。
高橋氏:当社は組織が大きく、カンパニー制ですので、事業ごとに分かれている部分と、互いに共創しあう部分を作っています。後者としては、基幹事業として挙げている空間ソリューション、現場プロセスソリューション、インダストリアルソリューションでは複数のカンパニーが連携して実現していこうとしています。
大森氏:1つめはビジネスイノベーション本部。HomeXを主にやっています。データの取り扱いを決め、くらし空間でどうアップデートするかを考えています。またモビリティ領域では自動運転の技術開発を担当する部隊もいます。
2つめはテクノロジーイノベーション本部。これは次世代の電池等の材料やセンサーデバイスなどの先端研究に取り組む、本社の研究所です。
3つめは要素技術開発センター。現場プロセスソリューションなどにあたる要素技術を担っています。AIの要素技術、画像通信、音の技術など。実はパナソニックは昔から音の技術が強みですが、それをソリューション事業に展開しています。
他には東京にあるデザイン本部。若手5.6名に任せて、デザイン思考から自由な発想で開発をしています。将来のタネになる面白いことをやっていく本部です。自社だけではできないのでオープンな会社とやりとりして、将来に向けて面白いことをやっていこうと取り組んでいます。突然「こういうことを発表します」と言われてギョッとしたり、(笑)自由です。
またマニュファクチャリングイノベーション本部というのは独立しているので我々のセンターでは直接担当していませんが、革新的な生産技術や人に寄り添うロボティクス技術の研究開発を行っています。
高橋氏:もともと知財部門は1つでした。知財は10年先の事業戦略において重要と捉え、2014年に、未来のための知財の戦略立案をする戦略部門(イノベーション知的財産センター等)を立ち上げました。それ以外の特許出願など従来の知財活動は、パナソニックIPマネジメントという100%子会社をつくって分社化しました。私はこちらの所属です。人は日々の糧のことを考えながら未来の糧のことを同時に考えるのはなかなか難しいことですから(笑)。役割は違いますが同じ知財部門なので、現場では組織の壁を気にすることなく連携しています。

大森氏:知財部は私のいる戦略課と、他には各技術部門のポートフォリオを管理する課、また研究所の過去の特許をどのように活用するか検討する課があります。また全体を見る企画課は日頃の運営が主で、予算や事業計画の推進を担当しています。中でも戦略課が先ほどの10年後の将来を考える部隊。技術現場では自分のテーマについてはそれぞれの知財担当が知財戦略を検討していますが、我々はマクロの視点から調査をしています。
実は良い特許は出願されてから10年以上たってから有効になるものも多い。我々の資産も10年前に出願しているものがあります。よく10年前にこれを出していたなと思うような、時代を先取りした特許がこれから有効になることもあるし、今の出願が10年後に役立つこともある。他社もそうだと思います。だから時代の先端を行くGAFAなどをベンチマークし、どのような特許を申請しているかを追うことで、10年後の動向が見えることも多いのです。
大森氏:我々イノベーション推進部門は、CTOの宮部がかなり強く発信していることもあり、かなり意識が変わっています。大阪の西門真が拠点ですが、東京の浜離宮にも拠点があり、特に東京では若手中心で、ユーザーエクスペリエンス(UX)を重視し開発の手法をとっています。今までは開発の最適化を図るやり方に対してユーザー最適化を目指すやり方で、製品のアップデートのゴールがどうあるべきかを議論しています。ユーザー目線でどう暮らしが変わるか徹底的に試す。シリコンバレーの部隊がアジャイル開発をして日本でフィードバックするやり方も試しています。今までの、ハードに新しいハードがついたらそれでいいという考えではありません。
高橋氏:特に若手のみなさんは、部署にとらわれず横のつながりが強く、新たな価値を提供することを考える流れを感じます。内部でもそういうメンバーが揃ってきているのは嬉しいですね。IT関係出身のキーマンも少しずつ活躍していただいています。マネジメントの我々も新しい分野では新入社員みたいなもの。読書会をして、お互いに知識を高めたり、プロの考え方を聞いたりして学びあってフランクに聞ける風土になっています。
大森氏:UXから出てくることは抽象的になりがちなので、そこから発明のポイントを引っ張ってくるようにパナソニックIPマネジメントの人たちと協力しています。出願もかつてのやり方とは大きく変わっています。旧来は「我々はこういう製品を出します、新規機能はこれ、特徴はこれです」というやり方で出願していましたが、今は「アップデートされるとこういう世界が来ます」というところから始まり、「特徴はこれです」いう手法。日本知的財産協会でも、時代の変化の中での申請方法については検討されています。

大森氏:私は研究所出身ですが、研究所はずっと自由でした。こういうテーマをやりたいといってダメと言われたことはなかったですね。
高橋氏:昔からキャリアパスも割と自由だと思います。例えば大学で生物を学んだ人でも努力すればUIの仕事ができる。社内においては縦割りだけということもなく、多様性を受け入れていると思います。最近はさらに多様性が広がっています。失敗してしまった人がいても切り捨てる雰囲気でもなく、上司に意見も言える環境です。もちろん社会人として、パナソニックの社員としての節度は守らなければならない。創業者の理念は、全世界のリーディングカンパニーも勉強してくれている大切なもの。そこは変わりません。
高橋氏:ずっと知財にいる人は多いですが、最近はもっと事業の中枢や戦略に関わっていくということで、経営企画や技術企画に異動する人もいます。昔から事業、技術、知財の戦略が三位一体と言われていますが、より知財の人が加わりやすい形になっています。知財の方に人事が伝えているのは、まず自らがキャリアのデザインを描いてくださいということ。その手助けとして先人のキャリア、この人はこういうところでこういう経験を積んでいるというようなアドバイスします。それを見て何年後はこういう人物になっていきたいとキャリアを描く。それをサポートするのが我々です。今年から新たに新入社員から30歳までの若手育成の10年計画を立てようとしています。ですから自分がどうなりたいかを考えられない人は厳しい。それを考えられる人にはチャンスはいくらでもあります。
大森氏:知財は新しい分野が多く、技術が変わっていくので、挑戦する意欲がある人が第一。他社の分析もやりますし、10年後の知財活動を牽引する力も必要です。特許出願経験と同時に自分が発明する経験もあるといいと思います。発明経験がない人はなかなか新しいことも出願を引っ張るのは難しい。そこは知財担当としては重要視しています。
例えばベンチマークする他社はどんな出願をしているか研究し、我々はどうするべきか知財の専門家と議論して技術部門にお願いする役目もあります。詳細な例だと最近のAIのアルゴリズムはクラウドの中で処理されていて、使って何ができるかがポイントになってきています。我々もクラウドの中の処理だと、特許を持っていたとしても他人が使っているか判別しづらいので、我々はその辺の出願をほとんどしないことにしている。AIは処理するだけでそのインとアウトだけに特徴付けるとして出願をしましょうと技術部門に頼んでいます。そういう分析などは戦略が絡んでくる。一定のベンチマーク解析だけでなく実際こうしましょうというところまで行くので、経験は豊富な方が嬉しいですが、実際には少ないと思いますのでチャレンジ精神がある人がいいですね。
大森氏:そこももちろん大事ですが、戦略的な考えをできることが大事だと思います。技術の人に考えてくださいと言うだけでなく、具体的な示唆を出せる方。そのまま使えるような発明でなくとも、自分で考えて示唆すると技術の方も触発されて良いものが出てくることがあります。そういうことができる人が嬉しいですね。ワークショップをやる場合のファシリテーターだけでなく、面白いアイディアを出すのも我々の仕事の一部。常識に囚われず、突拍子も無いアイディアを出せる方も嬉しい。例えば自身の経験や、ちょっとした世の中のトレンドを元に話を広げるなど、アイディアのタネを積極的に発言できるような方を求めています。
高橋氏:具体的なデータや情報を抽象化して、将来こういう方向に時代やニーズが向かうのではないかと仮説をたてて、その抽象化したものを具体化する思考が重要になると思います。
大森氏:そのような局面もあるかもしれませんが、得意な人がいますから補完ができます。新しい分野に対して、弱いのは当然。逆に従来の社員はハードのことは強いが、お互いに補完して、必要なことは勉強すれば良いと思います。ビジネスイノベーション本部でも、我々の知らない経験をしているIT系の方が加わっています。知財もソフト関連出身の方は大歓迎です。

大森氏:イノベーション推進部門は、我々のパナソニックの中でも先進的に新しいことにどんどんチャレンジしていく部門。日本のメーカーという枠を外しても面白いことをしていると自負しています。多分やったことのないことばかりを、1から作ることになると思いますが、とてもやりがいがある仕事です。自分で様々なことを考えて、動ける自由なポジション。知財戦略を策定する経験もできる、自由も高いが責任もある。研究所なので5年10年後に貢献できる仕事ができる。
例えば10年後の世界をテーマに、技術だけでは難しいので別の部署や外部の情報をもっている人とワークショップやってアイディアを出すなんてことも出来ます。一般的には、知財戦略で10年後を見据えた働きをすることはできないと思いますが、我々はそれが可能です。
高橋氏:はい。そういう経験もできる一方、当社はたくさんの事業の集まりであり、広い事業と広い技術を持っているので、あなたの知的好奇心は絶対に満たされるでしょう。当社では1つの単体企業では経験できない、複数の企業で経験するようなことを1社で経験することができ、幅広い知見を得ることが出来ます。ぜひチャレンジをお待ちしています。
ハイクラス転職で求められることは、入社後すぐにビジネスを牽引する存在になること。
そのために「コンサルタントの提案」を聞いてみませんか?
ご経験・ご経歴・ご希望などから、転職後のご活躍イメージを具体的にお伝えします。

転職支援サービスお申込み