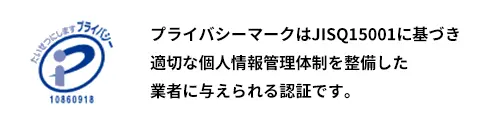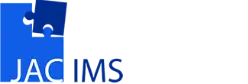JACは管理職・技術/専門職転職の
エキスパートです
JACがお預かりしている求人の一部を
ご覧いただけます
- 業種から探す
- 職種から探す
- 勤務エリアから探す
- 経験・スキルから探す
ハイクラス転職のJAC。
3つの特長とは

管理職・専門職のハイクラス転職に特化
日本で事業をスタートした1988年より、各企業に対して採用コンサルティングを実施してきたJACは、企業の採用責任者と強固な信頼関係を築いています。これにより、管理職やエグゼクティブ、技術職のような専門職の領域に特化した転職支援サービスにおいて、多くの実績をもっています。

転職のプロが複数人であなたをサポート
業界・職種に精通し、高い専門性を備えたコンサルタントが1,400名以上在籍。たとえば、医療業界出身の医薬バイオ専門コンサルタントや、金融業界20年以上のシニアコンサルタントなど。各業界のプロがあなたの市場価値を正しく理解し、業界を超えて、あなたのスキルと経験を発揮できる求人を紹介します。

外資系企業・グローバル企業への転職支援実績多数
ロンドン発祥の日系転職エージェントであり、世界に広がる独自のグローバルネットワークを有している背景から、JACは外資系企業や海外進出企業への転職支援で豊富な実績を重ねてきました。
求人の種類や数だけでなく、英文レジュメ作成や英語面接対策の支援にも強みをもっています。